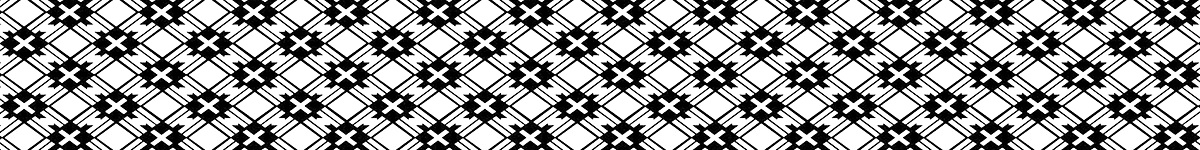


昨年4月、「夏の浴衣」から始まった、竺仙五代目・小川文男社長に学ぶ“きもの指南”も、今回が最終回。
第6回は、春先の反物と“誂え”について話を聞いた。
「2月になると、同じ冬でもちょっと違う感じがしますね。竺仙でも明るめのものを先取りで展開し始めています。風呂敷もピンク。これからの季節にちょうどいい色合いです。松竹梅もはいっておりますし、春はお祝いごとも多ございますから、ハレの日にふさわしいですね。吉祥ものの代表である松の柄もいいですね。こちらは『三階の松』といって、三層に重なった松の枝が描かれます。『傾城(けいせい)反魂(はんごん)香(こう)』ですとか、歌舞伎や人形浄瑠璃の舞台でもよく使われますね」
松は季節を選ばず1年中いつでも良いが、ハレのシーンには松がふさわしい。

風呂敷「金霞」(90×90cm)3,500円

風呂敷「鶴亀」(90×90cm)3,500円
「火消しの連中の纏(まとい)の柄の手ぬぐい、これは、5月の祭りの時期か正月が、いかにもらしい。季節感をストレートに出せるのがいまの季節なんです。昨今は、日本の季節は夏と冬だけになってきてしまっています」

手ぬぐい左から「梅に福寿草」1,250円、「纏」1,400円。
季節が春に向かうと、柄も春らしいものに。人が多く集まる場所にはお雛様も飾られるようになり、お雛様の掛け軸もお目見えするようになった。
「最近では、お召し物に、“際物”を求めるかたが増えていますね。クリスマスのサンタクロース、トナカイですとか。帯ならまだ許されるのではないかと、かなり際物のモチーフを使うようになってきました。西洋のものをジャパンナイズさせるというのはなかなか難しいのですが、みなさん楽しんでいらっしゃいますね。ある種の贅沢です。でも本当の贅沢というのは実は“誂え”なんです。いまは、“誂え”をされるお客様が減りましたね」
“誂え”とは、要するに特注である。洋服でいうとオートクチュールといったところか。この“誂え”が職人の腕を育ててきたと小川社長は言う。
「着物の知識があって初めて“誂え”ができるんです。たとえば友禅。柄の縁取りに、職人は糸目といって細い線を使うのですが、縁取りすることが難しいことがわかっている方は、絶対に伏せ糊でやってちょうだいだとか、あるいは糸目は糊で残して頂戴ねとおっしゃる。そういうようなことを言われると、職人は普段糸目糊を使わなくても、そのときだけは使わないといけません。それによって職人は技術を維持することができる。職人の腕が育つわけです。最近は確かに“誂え”が少なくなってきています。でもそれは、単に贅沢がなくなったということではなくて、どうやってものが出来上がるのかというからくりを知らない方が、ものすごく増えてきているということなんですね」
これは着物に限ったことではなく、あらゆるものがそういう傾向にあるとも話す。
そして残念なことに、それに伴い、知らないがために苦情をおっしゃるお客様が増えてきたとも。
「なんで色が落ちるの? 着物を吊っておいたら袖が袋になっちゃったとか。そういう苦情です。本来、表と裏の生地が違う着物は、それぞれの生地の伸縮も違います。だから、袖の先端が丸くなる。それを袋になったというのですが、作られる過程を知らないから、なんで表と裏と寸法が違っちゃったの?って苦情になる。そういう方が結構多いんですね。ですから着物を学んで、“誂え”というものを是非皆様にやっていただきたい」
靴やバッグの“誂え”のように着物にも、と言う。
「“誂え”ができるお客様は一流とわれわれは思っているわけです。手作りには、いい面と悪い面と両方がある。弱みももっていますから弱みの部分がわかってもらえないと本当の意味での手作りの良さはわかってもらえないんです」
最近では、来店し、小紋や友禅がどういうふうに出来たのか、いつから作り始めたのかなどを勉強するお客様もいるとか。そして、ブログに上げたり、SNSで発信するという。知ればわかるようになる。わかるようになれば注文ができる。“誂え”の文化を復活させて職人の技術を維持、向上させることが着物の将来に必須なのである。
最後に小川社長に、春らしい組み合わせの着物をご紹介いただいた。

「文久小紋 松竹梅」280,000円

「手書き友禅染め名古屋帯 つるしびな」160,000円
着物は、文久時代に流行した文久型。焼き物のデザインに似ている。二枚の型で彫り分けて模様ができる。
帯はかわいらしいつるしびな柄をあわせて。

「江戸小紋 梅唐草」290,000円。

「琉球紅型染め名古屋帯 霞の牡丹と蝶と桜」310,000円。
着物は、いわゆる江戸小紋より大きいが浴衣柄よりは細かい中小紋。梅のリピートが遠目に美しい。
帯は、色合いが春らしい。同じ赤の発色でも、沖縄の強い紫外線の中で見ると違う。小紋の型を作る刃は非常にデリケートだが、紅型は包丁に近いような刃で型紙を作るから無骨な線になる。この無骨な線が強い色にぴったり合う。帯地は氷割。氷が割れたような風合からそういわれる。
