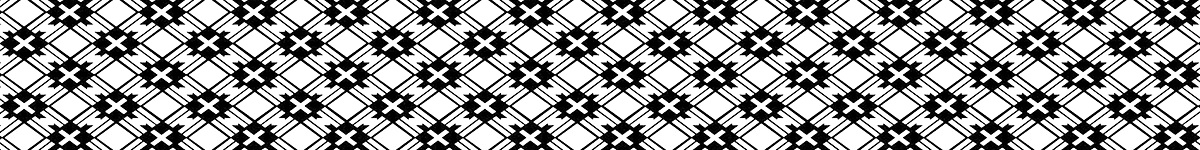


江戸明治から伝わる江戸染浴衣の技術をいまに受け継ぐ「竺仙」は、1842(天保13)年創業。竺仙独自の江戸染浴衣について、また夏を先取りして装う初夏の新作浴衣について、五代目小川文男社長に話を聞いた。
「浴衣は盛夏ものとなっていますけれど、浴衣には5月の三社祭の浴衣姿や、お相撲の五月場所の頃に両国橋を関取が浴衣掛けで歩いていく姿に夏を感じさせたという歴史があります。ところが温暖化の影響もあって、浴衣の時期としてはちょっと早いんですけれど、2、3月ごろでも1日数名のお客様がお見えになられて、旬なものや新柄をお求めになられます。どうも今の方は浴衣を“木綿の単衣の着物”と見る傾向があるようです。」
まだ肌寒い日もある5月だから襦袢を着て浴衣をというわけで、竺仙は、この時期にふさわしい「紬浴衣」を提案している。
「紬は、生地がぽてっとしていますから温かみがある。たまに暑い時もあるけれど、基本的には肌寒い、端境期の着物として適当だと思います。本来浴衣というのは襦袢を着てきるものではなく素肌に着るものなんですが、いまは浴衣に関する認識が変わってきているようです。“準着物”という言い方もおかしいですが、どこか着物を見る感覚で浴衣を見ていらっしゃる」
確かに薄手で張りのある盛夏の浴衣と比べると、紬浴衣はぽってりして手触りが温かい。
そして竺仙独特の、なんとも言えない柄の美しさである。

(左)左から「茶紬」宝相華柄40,000円、「紬浴衣」蝶々柄32,000円、「縮長板中形」流水に千鳥柄73,000円。
(右)ぽてっとした温かみのある生地の「紬浴衣」蝶々柄32,000円。
「ベースは江戸のデザインですが、完成したのは明治の初めです。明治維新以降は洋装の時代だと思われる方もいるでしょう。しかし江戸初期の慶長小袖をみても、安土桃山の派手なデザインがうかがえます。文化というのは元号が新しくなってすぐに変わるものでもなく、明治の初めであっても、江戸の香りがものすごく強いんです」

ぼかし染めが美しい「綿紅梅小紋」乱菊柄63,000円。

男性用紬浴衣。左から「細川染め」松トンボ柄と、格子柄。各40,000円。
では浴衣はいつごろ出来上がったのだろう。
「それは木綿の栽培が国内でできるようになった江戸の中期です。それまでは輸入なんです。またそのころ、染料の藍も国内でできるようになりました。こうして浴衣が出来て、それに合うデザインが生まれた。しかも作り手は庶民です。つまり御用絵師がデザインしたものじゃない。モチーフにしても蝶々、撫子…きわめて身近な素材がデザインになっているのが庶民のデザインの特徴です。だからものすごく理解しやすい。それが明治になると、日本人独特のデリケートなラインが生まれます。絵も繊細で、絵心がないと描けないような完成された形になっていきます。」
例えば今年の新作、大胆にあしらった牡丹に流水柄の紬着物が、いい例である。
「ここまでいくと、普通の絵描きじゃないなと思いますね。牡丹の花と流水を、まるで平安の頃に霞を描いて場面展開をさせたように配置させている。ここまで絵が複雑になれば、型紙を彫るにも、さまざまな部分の型紙を三枚、四枚と彫り分けて彫らなければいけません。なかなかの作業です」

牡丹の花と流水を、まるで平安の頃に霞を描いて場面展開をさせたように配置させた新作の「奥州絣」松煙染小紋、流水にぼたん柄66,000円。

「紬浴 衣」石蕗柄32,000円小川社長直々に浴衣を選んでもらう。「大きな柄がよくお似合いになりますよ」。
そしていよいよ染めであるが、これも江戸からの染めの本流「長板中型」に始まり、明治になって生まれた、染料を如雨露で注ぐ「注染」といった合理的な染め方まである。これは次回、再び小川社長に“盛夏の浴衣”を紹介いただく時に詳しく説明したい。
(文・織田桂 写真・泉大悟)
